三国志の軍師たちはなぜ「名言」が多いの?
ようこそ、三国志と名言の世界へ!
三国志といえば、魏・呉・蜀の三つの国が覇権を争った、アツ〜い時代の物語ですよね。登場する英雄たちはみんな個性的で魅力的ですが、彼らを影から(時にはド真ん中で)支えた「軍師(ぐんし)」たちの存在を忘れてはいけません!
軍師とは、簡単に言えば、戦のプロフェッショナル。戦略や戦術を考えたり、お天気まで見通したり(!?)、敵を騙したり、味方を鼓舞したり…。もう、やることなすこと規格外な人たちでした。
そして、彼らの超絶ヤバいスキルの一つが、何を隠そう「言葉の力」だったんです。主君に危険な進言をする時、兵士たちの心を一つにする時、絶体絶命のピンチを打開する時…。彼らの言葉は、剣や槍よりも強力な武器となりました。だからこそ、彼らが放った言葉は、時代を超えて私たちの胸にも響く「名言」として残っているんですね。
この記事では、そんな三国志の軍師たちの言葉を深掘り!現代のビジネスシーンや人間関係にもガンガン使える、目からウロコな教訓がいっぱいありますよ。まるでタイムマシンに乗った気分で、彼らの「言葉の武器」を学んでみましょう!
軍師たちの言葉は、時を超えて、今もあなたを支えるヒントになるかもしれない。さあ、一緒にタイムスリップしてみよう!
📺動画でも解説中!
「軍師名言ってなに?」と思ったら、この1分動画を見てスッキリ!
記事のポイントや裏話をサクッとまとめています👇

利を見ては動くべし!お得な情報、見逃すなよ?」
※この記事には曹操様も納得(?)なPRリンクが含まれています。
三国志 ヤバすぎ軍師名言5選とその意味・教訓
お待たせしました!ここからは、三国志に輝く数多の軍師たちの中から、特に私たちの心に刺さる「ヤバすぎ名言」を残した5人を厳選してご紹介します。彼らがどんな状況で、どんな思いでその言葉を発したのか?そして、それが現代を生きる私たちにどんな学びを与えてくれるのか?じっくり見ていきましょう!


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
ふむ、ここで紹介される奴らは、ワシから見ても確かに一癖も二癖もある奴らじゃな。まあ、ワシが一番じゃが。
さあ、まずはこの人から!
軍師 諸葛亮の名言:「静以修身、倹以養徳」(せいをもってみをおさめ、けんをもってとくをやしなう)

三国志の軍師と聞いて、真っ先にこの人の顔が浮かぶ人も多いはず!蜀を建国した劉備を支え、「天下三分の計」を実行に移した天才、臥龍こと諸葛亮孔明です。常に冷静沈着で、神算鬼謀のイメージが強い彼ですが、意外にも(?)自分自身を律することの重要性を説いています。それがこの言葉です。
「静以修身、倹以養徳」(せいをもってみをおさめ、けんをもってとくをやしなう)
意味: この言葉は、諸葛亮が晩年、息子である諸葛瞻(しょかつせん)に送った『誡子書(かいししょ)』という手紙の中の一節です。「心を静かに落ち着かせることによって自己を修養し、また、つつましく倹約に努めることによって人としての徳を養いなさい」という意味。つまり、外側を飾るのではなく、まず自分の心と生活を整えることが、人間的な成長には不可欠だ、と説いているわけです。
背景: 諸葛亮がこの手紙を書いたのは、彼自身が丞相という激務に追われる中で、自らの経験から得た人生哲学を息子に伝えたかったからでしょう。戦場や政治の駆け引きは常に激しく、感情的になりやすいもの。しかし、彼はどんな時も冷静さを失いませんでした。その秘訣が、日頃から「静」と「倹」を心がけるという自己管理にあったと考えられます。私利私欲に走らず、感情に流されず、常に大局を見て正しい判断を下すには、まず自分自身の内面を律する必要がある、という彼自身の生き様が反映された言葉と言えます。
教訓: この言葉は、リーダーにとって最も根源的な資質である「内面のコントロール」の重要性を教えてくれます。感情に任せて怒鳴ったり、目先の誘惑に負けたりするようでは、誰もついてきません。また、組織を率いる立場になれば、自分の言動がチーム全体に大きな影響を与えます。だからこそ、常に冷静であること、そして私生活も含めて自分自身を律する姿勢が不可欠なのです。「リーダーの品格は、その内面から滲み出る」と言っても過言ではありません。
今に活かす: 現代社会は情報過多で、ストレスも多いですよね。ちょっとしたことでイライラしたり、SNSで感情的なコメントを書き込んでしまったり…。そんな時こそ、諸葛亮の「静以修身」を思い出しましょう。まずは深呼吸。感情的になる前に一呼吸置く習慣をつけるだけでも、人間関係のトラブルは減るはずです。また、「倹以養徳」は、単なる節約だけでなく、無駄なものに振り回されず、本当に大切なものに集中するという考え方にも繋がります。情報ダイエットや時間管理にも通じる、現代にもめちゃくちゃ役立つ教訓と言えるでしょう。感情に流されない冷静な判断力は、現代の複雑なビジネス環境を生き抜く上でも、管理職だけでなく全ての働く人にとって大切なスキルです。
🔗 あわせて読みたい!
「えっ、死んだ孔明に司馬懿が逃げた!?」という有名すぎる名言
【死せる孔明、生ける仲達を走らす】。
木像エピソードの真相や、史実との違いなどをちびキャラと一緒に爆笑解説しています
「泣いて馬謖を斬る」って実は、ただの悲しい話じゃない!?
諸葛亮の苦渋の決断と、そこに込められた深い教訓を、かわいいちびキャラたちと一緒に楽しく学べる記事はこちら!

え、丞相、僕、ちゃんと山の上に静かにしてましたけど…?耳塞いで…。

お前は耳を塞いで心を動かした!本質を見ぬ凡人め!
軍師 荀彧の名言:「小さな義を捨て、大きな義を取る」

魏の武帝・曹操の天下統一事業を、まさに軍師としてだけでなく、戦略、人事、内政あらゆる面で支え続けたキーパーソン、荀彧(じゅんいく)。彼の判断基準を示すかのような、非常に重く、時に非情とも捉えられる言葉です。
「小さな義を捨て、大きな義を取る」
意味: この言葉は、荀彧が曹操の行動に対して意見を述べたり、ある出来事を評価したりする際の基準として彼自身や周囲が用いた考え方です。(※諸葛亮のように本人から発せられた手紙の一節というより、その行動原理を端的に表したフレーズとして知られています。)個々の、あるいは目先の「正しいこと」(小さな義)に固執せず、天下全体を安定させる、あるいは自らが仕える主君(曹操)の正義を貫くという「大きな目的(大きな義)」のために、個人の感情や一部の犠牲はやむを得ない、という決断を下すことを意味します。
背景: 荀彧が生きた時代は、天下が乱れ、多くの民が苦しんでいました。彼は漢王朝への忠誠心を持ちつつも、その中で曹操こそが天下を安定させられる器だと見抜きました。**しかし、**曹操のやり方は、時に非道とも思えるものでした。例えば、徐州での大虐殺に対する曹操への諫言。荀彧は曹操の行為を厳しく批判しましたが、最終的には曹操から離れることはありませんでした。これは、曹操を見限るという「小さな義」よりも、曹操という力をもって乱れた世を収めるという「大きな義」を選んだと解釈できます。彼の苦悩は計り知れません。**したがって、**この言葉の背景には、理想と現実の狭間での深い葛藤があったと言えます。
教訓: 組織や社会全体の利益のためには、個人の感情や一部の利益を犠牲にせざるを得ない場面が必ず出てきます。リーダーや責任ある立場にいる人は、往々にして「小さな義」と「大きな義」の間で難しい選択を迫られます。目先の人間関係を壊したくない、一部の反対意見を無視できない…といった感情に流されず、組織全体の、あるいはより高次の目的を達成するために、たとえ非難されることになっても、必要な決断を下す胆力と覚悟が求められる。これがこの言葉から学べる厳しい教訓です。
今に活かす: 現代のビジネスシーンでも、この「小さな義」と「大きな義」の選択は頻繁に起こります。例えば、不採算部門からの撤退、リストラ、新しいシステムの導入による一時的な混乱、あるいはあるプロジェクトの成功のために、特定の部署に大きな負担をかける決定などです。「あの人の部署が大変そうだから…」と立ち止まるのは「小さな義」に囚われている状態かもしれません。プロジェクト全体の成功や、会社の将来という「大きな義」を見据えて、必要な判断を下す。このように、荀彧の言葉は、組織の中でリーダーが苦渋の決断を下す際の、覚悟の重要性を問いかけてきます。もちろん、そこには決定に至るまでの十分な議論と、決定後の丁寧なフォローが伴うべきですが。

ふーん、めんどくさいこと考えるね。私は自分の『義』が一番大きいけど?だって天才だし。
▼荀彧ってどんな人物?が気になったらこちらもチェック!
▶️🔗 荀彧はどんな人?曹操が頼りにした「王佐の才」の素顔と最期とは
曹操を支えたのは、一癖も二癖もある「天才軍師」たちでした。 あなたの推しが見つかるかもしれない、最強の頭脳集団ランキングはこちらからどうぞ!
▶️🔗【曹操軍】軍師ランキングTOP10!なぜ魏は強かったのか?
軍師 周瑜の名言:「大丈夫、我に策あり」(創作ベース)

赤壁の戦いで、あの曹操の大軍を打ち破った呉の若き総司令官、周瑜(しゅうゆ)!「美周郎」と呼ばれるほどのイケメンで、文武両道。完璧超人っぽい彼ですが、実は感情豊かな一面も。そんな彼のイメージにぴったりの、創作ベースながら非常に人気の高い、聞くだけで安心できる名言です。
「大丈夫、我に策あり」
イメージ名言: これは、三国志演義などで描かれる周瑜が、絶体絶命のピンチや、味方が動揺している場面で、自信満々に発するセリフとして有名です。「心配するな!この私には、この状況を打開する完璧な策がある!」という強い意志と、周囲を安心させるリーダーシップが感じられる言葉です。
背景: 周瑜が活躍した赤壁の戦いは、圧倒的な兵力差のある曹操軍に対し、孫権・劉備の連合軍が挑んだ文字通りの大ピンチでした。内部には弱気な意見も多く、連合軍全体が不安に包まれていました。その中で、総司令官である周瑜が、病に苦しみながらも毅然とした態度を保ち、「私は勝てる」という確信(そしてそれを可能にする緻密な戦略)を示せたことが、連合軍の士気を保ち、勝利に繋がった大きな要因の一つです。この言葉は、その時の彼の「指揮官としての姿勢」を象徴していると言えます。
教訓: リーダーがパニックに陥ったり、弱気な姿を見せたりすると、チームは簡単に瓦解してしまいます。周瑜の言葉は、どんな困難な状況でも、リーダーは感情をコントロールし、毅然とした態度でチームに「安心感」を与える存在であることの重要性を教えてくれます。そして、その「大丈夫」という言葉の重みは、日頃からの徹底的な準備や、困難を乗り越えるための具体的な戦略を持っているからこそ生まれるのです。「言うだけでなく、ちゃんと策がある」という裏付けがあってこそ、リーダーの言葉は力を持ちます。
今に活かす: 現代のビジネスシーンでも、プロジェクトの遅延、予期せぬトラブル、競合の出現など、様々なピンチが訪れます。そんな時、リーダーであるあなたが「どうしよう…」とオロオロしていたら、部下はさらに不安になりますよね。たとえば、「この問題は想定内だ。A案とB案、二つの解決策を用意しているから、まずはA案でいこう。もしダメでもB案がある。」のように、具体的な手立てを示すことで、チームは落ち着きを取り戻し、前向きに問題解決に取り組めます。周瑜のように、常に先を読み、複数の選択肢を用意しておく「戦略眼」と、それを冷静に伝える「言葉の力」は、現代リーダーに不可欠なスキルと言えるでしょう。

ふむ…その『策』とやら、私が考えてあげても良いですよ?フフフ…。

孔明め!私の策じゃ!
関連記事👇
周瑜の本当の姿、知ってますか?赤壁の戦いでの活躍から意外な素顔まで、7つの真実をわかりやすく解説しています。歴史ファンも初心者も必読!
▶️🔗 周瑜の生涯と赤壁の戦い|知るべき7つの真実
軍師 龐統の名言:「臥龍鳳雛、いずれかを得れば天下を得ん」(司馬徽)

諸葛亮と並び称され、「鳳雛(ほうすう)」と呼ばれたもう一人の天才、龐統(ほうとう)。見た目は地味…というか、正直パッとしない感じだったと言われていますが(失礼!)、その才能は諸葛亮に匹敵すると評価されていました。彼に関連する最も有名な言葉がこれです。
「臥龍鳳雛、いずれかを得れば天下を得ん(がりょうほうすう、いずれかをえればてんかをとらん)」
意味: この言葉は、隠者である司馬徽(しばき)が、まだ世に出る前の諸葛亮(臥龍=隠れた龍)と龐統(鳳雛=若い鳳凰)という二人の抜きん出た才能を持つ人物を評して言ったものです。「この二人のうち、どちらか一人でも味方につけることができれば、天下を取ることができるだろう」という意味。つまり、それほどまでに、優れた人材の存在が天下を左右するほど重要である、ということを端的に示しています。
背景: 三国志の時代は、まさに人の才能が国力に直結する時代でした。どれだけ兵力や土地があっても、それを活かす知恵や勇気を持つ人物がいなければ、天下を争うことはできません。司馬徽は、まだ世に知られていなかった諸葛亮と龐統の中に、その「天下を取るに足る才能」を見抜きました。**しかしながら、**才能ある人物を見抜く「目」と、彼らを自陣に迎え入れる「力」がなければ、その言葉は何の意味も持ちません。劉備が三顧の礼で諸葛亮を迎え入れ、苦労して龐統を仲間に加えたエピソードは、まさにこの言葉の重要性を体現しています。龐統自身も、最初に仕官した孫権には才能を見抜かれず、劉備の元でも最初は冷遇されるなど、その才能が認められるまでには苦労がありました。
教訓: この言葉は、組織にとって最も重要な財産は「人材」であること、そしてその才能を見抜く「人を見る目」と、チャンスを逃さず優れた人材を仲間に引き入れる「機会を掴む力」の重要性を教えてくれます。どんなに立派な戦略も、それを実行できる人間がいなければ絵に描いた餅です。優秀な人材の獲得と育成こそが、組織を成長させる上で最も根幹となる課題なのです。
今に活かす: 現代のビジネスシーンにおいても、「人材こそが企業の成長エンジン」と言われます。採用活動はもちろんのこと、今いる社員の中に眠っている才能を見つけ出し、適切に配置したり、育成したりすること(=人材投資)は、競争力の維持・向上に不可欠です。また、新しい事業やプロジェクトを立ち上げる際、優秀なパートナーや専門家を見抜いて協力を取り付ける「スカウト力」も非常に重要です。**このように、**龐統にまつわるこの言葉は、「あなたの周りにも、まだ見ぬ臥龍や鳳雛がいるかもしれない。彼らを見つけ出し、その力を借りる準備はできているか?」と問いかけてくるようです。

え、僕ももしかして鳳雛かも?でも寝るのが得意なだけだしなぁ…。
軍師 陸遜の名言:「小事に惑わされず、大事を成す」

呉の孫権に見出され、若くして大都督に抜擢された天才、陸遜(りくそん)。彼は、古参の将軍たちの嫉妬や、強敵からの挑発といった「小事」に一切動じず、関羽撃破や劉備の大軍壊滅という「大事」を成し遂げました。彼の冷静かつ大胆な指揮ぶりを表す言葉です。
「小事に惑わされず、大事を成す(しょうじにまどわされず、だいじをなす)」
意味: この言葉は、陸遜が夷陵の戦いで劉備率いる蜀の大軍と対峙した際の、彼の戦術と精神状態を端的に表しています。劉備軍は、暑さに苦しむ呉軍を焦らせようと、陣を細かく分け、挑発を繰り返しました。呉軍の将兵たちは怒って反撃を叫びますが、陸遜は劉備の狙いを見抜き、一切応じません。そして、暑さで油断しきった劉備軍に対し、大規模な火計で大勝利を収めます。「目先の些細な出来事や、感情的な誘いに振り回されることなく、本質を見極め、最終的な最も重要な目的を達成する」という意味です。
背景: 陸遜が大都督になった時、彼はまだ若い世代でした。年上のベテラン将軍たちからは軽んじられ、指揮下に入るのを渋られるという「小事」がありました。また、敵である劉備からの連日にわたる挑発も、普通なら感情的に反応してしまうような「小事」です。**しかし、**陸遜はそういった周囲の雑音や目先の出来事に一切囚われず、孫権から与えられた「蜀軍を撃退し、呉を守る」という「大事」の達成のみに集中しました。彼のこの冷静さ、そして「大事」を見失わない強い意志と洞察力が、呉を最大の危機から救ったのです。
教訓: 私たちの周りにも、毎日様々な「小事」が溢れています。些細な人間関係のいざこざ、無関係な噂話、目の前の小さなトラブル、ついつい見てしまうネット記事…。これらの「小事」に気を取られている間に、本当にやるべき「大事」(仕事の目標達成、大切な人間関係の維持、自己成長など)がおろそかになってしまうことはよくあります。陸遜の言葉は、「今、自分が何に時間とエネルギーを使うべきか、本質を見極めろ」という強いメッセージを私たちに送っています。感情的な反応や目先の誘惑に惑わされず、常に最終目標を見据える胆力の重要性を教えてくれます。
今に活かす: 日々の業務に追われていると、メールチェックや電話対応、定例会議など、目の前のタスクに忙殺されてしまいがちですよね。**しかし、**それらの「小事」が、会社や部署全体の目標達成という「大事」にどう繋がるのか、常に意識することが重要です。陸遜のように、「これは本当にやるべきことか?」「もっと効率的な方法はないか?」と立ち止まって考える習慣をつけることで、限られた時間とエネルギーを最も重要なことに集中させることができます。日常業務の「小事」と、会社全体の戦略的思考の「大事」のバランスを取り、本質を見極める力は、現代の忙しいビジネスパーソンにとって非常に重要なスキルです。

小事に惑わされず…?俺様の小事がデカすぎたんだよ…!ってか若造にやられるとは…!
関連記事👇
派手さはない。でも、彼がいなければ呉は滅んでいた。
“静かに勝つ男”陸遜の人生から、リーダーの真髄を学ぶ
▶️🔗 陸遜とは?三国志の呉を支えた“炎の知将”をやさしく解説
現代でも使える!軍師名言の活用術

🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
名言は“読むだけ”じゃもったいない。日常で使ってこそ、その真価を発揮するんじゃ。ワシのスタンプも使うがよい!
どれもこれも、胸の奥の方にズシンと響くような、重みのある言葉ばかりですよね。
でも、ここで「ああ、いい言葉を聞いたなあ」と感心して、そのままお布団に入ってしまうのは、ちょっともったいないんです。
せっかくの素晴らしい知恵も、使わなければ宝の持ち腐れ。買ってきた高級なスパイスを、棚の奥にしまい込んでしまうようなものですから。
現代の私たちの生活も、ある意味では戦場みたいなものです。
たとえば、リモートワークでのチャットのやり取り。顔が見えない分、ちょっとした言葉の選び方で誤解が生まれたり、冷たく感じられたりすること、ありますよね。
そんな時こそ、軍師の出番です。
会議でピンチに陥った時、心の中でそっと「大丈夫、我に策あり」とつぶやいてみる。
実際に策があるかどうかは置いておいて、そう構えるだけで、不思議と呼吸が深くなって、落ち着きを取り戻せたりするものです。
もっと手軽な方法もありますよ。
気に入った名言を、スマートフォンの待ち受け画面に設定してみてはどうでしょう。
私たちは一日になんどもスマホを見ますよね。
イライラしてつい感情的になりそうな時、画面にパッと「静以修身(静をもって身を修む)」なんて文字が出てきたら、「おっと、いけない」とブレーキがかかるかもしれません。
いわば、心の安全装置ですね。
それに、最近は三国志のLINEスタンプも充実しています。
後輩を褒める時に「素晴らしい!」と文字で送るより、孔明が羽扇を振って褒めているスタンプを送るほうが、なんとなく場が和みますよね。
「なんだこれ(笑)」とクスッと笑ってもらえたら、それだけでコミュニケーションという戦は大勝利です。
遠い昔の英雄たちの言葉ですが、博物館に飾っておく必要はありません。
ポケットに入れて持ち歩いて、疲れた時にキャンディのように舐めてみる。
そうやって彼らの知恵を日常に混ぜ込んでいくと、明日からの景色が、ほんの少しだけ頼もしく見えるはずですよ。

賈詡様のスタンプ?『まあ、なんとかなるじゃろう』…うーん、励まされてるのか…?」
ちなみに、今回の軍師たちに興味を持った方は、彼らの活躍をもっと深く知るためにおすすめの書籍もチェックしてみてください!
私が思わず笑ったり、泣いたり、吹き出したのがこちら👇
▶️ 🔗 三国志おすすめ本ベスト【7選】初心者から沼落ちまで
中でもおすすめは、『眠れなくなるほど面白い三国志』!👇
▶️ 🔗 三国志 わかりやすい本ならコレ!眠れぬ夜が続く「意外な1冊」とは?
読みながら、「司馬懿ってこんなに人間くさかったの!?」
「孔明って本当に死んでからも動くの!?」
とツッコミたくなる場面が満載でした(笑)
初心者でもスイスイ読めるのに、気づけば深みにハマってしまう一冊です。
「三国志って難しそう…」と思ってる人ほど、この1冊でイメージが変わりますよ!

馬に乗ってても読んじゃったわ!そしたら、木にドーンよ!!(ドーン)
👇【簡単リンク】『眠れなくなるほど面白い三国志』
(楽天/Yahoo/Amazonから選べます)
【まとめ】あなたの推し軍師はどのタイプ?


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
タイプは違えど、どの軍師も深い“知恵”を持っておる。己に合う名言を羅針盤とするがよいぞ。
今回は、諸葛亮、荀彧、周瑜、龐統、陸遜という、個性豊かな5人の軍師たちの「ヤバすぎ名言」と、その現代への活かし方を見てきました。いかがでしたでしょうか?
冷静な自己管理を重んじる諸葛亮タイプ、大局のためなら非情な決断も辞さない荀彧タイプ、自信と戦略でチームを牽引する周瑜タイプ、隠れた才能を見抜く龐統タイプ、目先のことに惑わされず本質を見抜く陸遜タイプ…。
このように、それぞれの軍師が持つ考え方や価値観は、現代を生きる私たちにも様々なヒントを与えてくれます。あなたが「この言葉、自分に一番刺さる!」「この軍師みたいなリーダーになりたい!」と感じたのは誰でしたか?ぜひ、あなたの「推し軍師」を見つけて、その言葉を日々の羅針盤にしてみてください。
**そして、**もしよろしければ、コメント欄であなたがどの軍師の名言に一番グッときたか、その理由なども含めて教えてください!「この名言、あの時の自分に聞かせたかった…」みたいなエピソードも大歓迎です!読者の皆さんのコメントも、きっと誰かの学びになるはずです。
**最後に、**軍師たちの名言や生き様を見て、「この人、自分に似てるかも?」「ちょっと憧れるな…」と感じた方もいるのではないでしょうか?
**そこで、**次回のシリーズでは、ちょっと趣向を変えて【性格診断】をお届け!
あなた自身の性格や考え方から、どの軍師タイプに近いかをズバリ診断しちゃいます!
「自分って、もしかして周瑜タイプのカリスマ?」「実は龐統みたいな切れ者かも…?」なんて、新しい発見があるかもしれません。

次回はついに…あなたの中に眠る“軍師力”がわかる!? 性格診断で、あなただけの推し軍師タイプを発掘しちゃうよ~!お楽しみにっ🐶✨

今回の名言、色々あったけど…結局、腹減ったな!おれの名言?『メシを食ってから考える』! これに勝る戦略なし!
👀おまけ:三国志をもっと深く楽しみたいあなたへ
三国志ファンなら一度は読んでほしい、「はじめての三国志」さん。
私自身も参考にさせてもらってきた大好きなサイトです。
👉詳しくはこちら🔗諸葛亮の不朽の名言集!現代にも響く智慧の言葉集
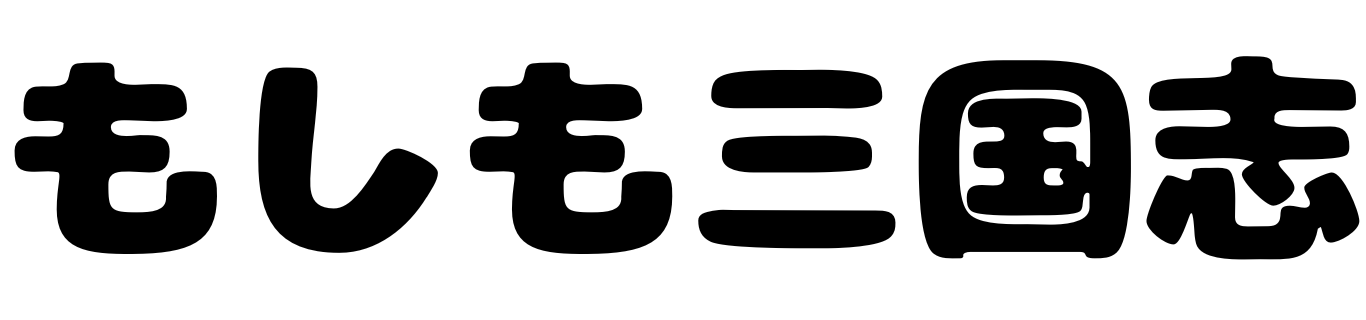












コメント