司馬懿とは?――三国志に出てくる魏の知略家で、「仲達(ちゅうたつ)」とも呼ばれます。
初心者のあなたは「名前は聞いたけど、なんか難しそうなおじいちゃん…」と感じていませんか?しかし安心してください!実は彼、「勝つまで動かん!」をモットーにした超ド級の忍耐型参謀。あの天才・諸葛亮を「もうやだ、帰る!」と言わせた唯一の男なのです。
この記事を読むと、「司馬懿って結局何をした人?」という疑問が一発で解消します。
しかも、彼の生涯や逸話をわかりやすく知ることで、三国志がグンと楽しくなるはず。なぜなら司馬懿は魏を実質支配し、孫の代で三国時代を終わらせた「歴史のエンディングメーカー」だから!さあ、一緒に笑いながら“動かない男”の秘密を覗いてみましょう!

利を見ては動くべし!お得な情報、見逃すなよ?
※この記事には曹操様も納得(?)なPRリンクが含まれています。
Q. 司馬懿の読み方は?「仲達」って誰? A. 「司馬懿」はしばい、字(あざな)は仲達(ちゅうたつ)。仲達=司馬懿です。
Q. 司馬懿はいつの人?生没年は? A. 後漢末〜三国時代の魏で活動。179年〜251年です。
Q. 司馬懿は何をした人?一言でいうと? A. 魏の知将。諸葛亮の北伐を守勢と消耗戦で防ぎ、のちに高平陵の変で実権を掌握しました。
Q. 諸葛亮の北伐は何回?どう防いだ? A. 一般に5回。正面決戦を避け、守備・補給妨害の持久戦で消耗させました。
Q. 「五丈原で司馬懿は何をした?」 A. 守備を固め決戦を回避。長期のにらみ合いの末、孔明の病没で蜀軍が退きました。
Q. 高平陵の変はいつ?かんたんに言うと? A. 249年のクーデター。司馬懿が曹爽一派を排除し、魏の実権を司馬氏が握る転換点です。
Q. 司馬師・司馬昭・司馬炎のちがいは? A. 司馬師=長子で政権運営の名手/司馬昭=次子で大胆に基盤固め/司馬炎=孫で晋を建国し三国終結。
Q. 「死せる孔明、生ける仲達を走らす」の意味は? A. 孔明の死後もその威光を恐れて司馬懿が退いたという故事。孔明の名声と司馬懿の用心深さを示します。
司馬懿はどんな人?【読み方・何した人・いつの人を超やさしく】


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
司馬懿は魏の忍耐型の知略家じゃ。読みは“しばい”・字は“仲達”、そして“待って勝つ”のが十八番じゃ。
司馬懿はどんな人?結論からいえば「動かないのに強い人」です!
「司馬懿(しばい)って名前は知ってるけど、なんか難しい顔のおじいちゃん…?」
初心者のあなたは、そう思って目を細めてませんか? でも安心してください!
まず結論。司馬懿は魏(ぎ)の国で頭角を現し、あの天才・諸葛亮(しょかつりょう)の北伐を、なんと**“動かない戦法”=守備と消耗戦**で跳ね返した知略家。そして最後には魏の実権をがっちり握り、孫の代で三国時代を終わらせる「知略のラスボス」なんです。
この記事では、初心者がつまずきやすい**「読み方」「何した人」「いつの人」**の3大疑問をサクッと整理!読めば三国志がグッとわかりやすくなり、しかも「なるほど、勝つまで動かんって意外と人生のヒントかも?」と元気まで湧いてくるはずです。
司馬懿の読み方と別名は?(司馬懿 読み方/別名=仲達)
さてさて、まず基本の「き」!この難しそうな名前、司馬懿(しばい)さん。読み方は「しばい」でスッキリOK👌。そして、ゲームやマンガでよく見る「仲達(ちゅうたつ)」という名前は、実はこの司馬懿さんの「字(あざな)」なんです!
「え、どういうこと?💦」って思いますよね?でも大丈夫!昔の中国では、本名(懿)のほかに、ニックネームみたいな公の呼び名(仲達)を使う慣習があったんです。だから、「仲達=司馬懿」と覚えておけば、もう三国志ツウの仲間入り!「司る馬の懿(よい)」で「しばい」!名前が難しそうでも、一度わかると一気に親近感が湧いて、なんだか元気が出てきませんか?
司馬懿の生没年・出身地・家柄まとめ(年表付き)
「この人、いつの人なのよ〜?」という疑問は、ざっくり年表で解決しちゃいましょう!
| 年代 | 出来事 |
| 179年 | 河南省温県で誕生!当時は名門のエリート坊ちゃん✨ |
| 200年代前半 | **曹操(そうそう)**に「イヤイヤながら」仕えはじめ、文官としてメキメキ頭角を現します。 |
| 220〜230年代 | **諸葛亮(しょかつりょう)**の攻撃に対し、「動かざる戦法」で対抗!粘り勝ちはお手のもの。 |
| 249年 | 高平陵(こうへいりょう)の変というクーデターで、サクッと政敵を排除!実権をガッチリ握ります。 |
| 251年 | 73歳で死去。しかし、ここからがすごい!息子(司馬師・司馬昭)、そして**孫(司馬炎)**へと権力は引き継がれ……。 |
そう、彼は名門生まれの超エリート!しかし、若い頃はなぜか病気を装って「ワタクシ、仕官なんて無理でして〜」と、のらりくらり仕官を渋っていたという伝説が!これも用心深さの表れでしょうか?(きっとそう!)この「のらりくらり」パワー、なんだか見習いたくなりますね!
司馬懿は何をした人?役割を3ステップで解説
じゃあ、結局司馬懿は何をした人? 役割は、**三段ロケット🚀**で考えると超カンタン!
- 🚀第一段階:文官期
- 法制度や人事で、頭の良さを発揮!優秀なサラリーマンでした。
- 🚀第二段階:軍事期
- 諸葛亮の北伐というピンチに登場!決戦を徹底的に避けて、補給線をイジメるという消耗戦で、相手が勝手にギブアップするのを待ちました。
- 🚀第三段階:実権掌握期
- 高平陵の変という一発勝負のクーデターで、ドーンと政権の主導権を司馬氏へ!そして孫の司馬炎が最終的に**晋(しん)**を建国し、三国志時代を終わらせることに成功!
つまり、司馬懿は「陰でじっくり準備→機が熟したら一気にドーン!」の人。正面から戦って勝つより、「相手がヘトヘトになるまで、お茶でも飲んで待つか🍵」という超絶忍耐戦法の使い手!これが“勝つまで動かん”の正体なんです。
ひとことで言うと:「絶対に負けない設計図」を描いて、「勝利をじわじわ引き寄せた参謀」!これって、なんだか人生を乗り切るヒントになる気がしませんか?
さあ、ここまでで司馬懿の読み方/いつの人/何をした人がスッキリクリアになりましたね!👍 次は、みんなが一番気になる「ライバル・諸葛亮との知略合戦」で、彼の具体的な戦い方をもっと笑いながらのぞいてみましょう!お楽しみに!🎉
関連記事👇
👉 「最強=ド派手に勝つ」だけじゃない!
じつは三国志には、司馬懿のように“負けない強さ”を武器にした武将たちもたくさんいます。そんな地味だけど恐ろしく強い武将たちをまとめたのがこちら👇
▶️🔗 三国志“負けない武将”史実よせ【TOP10&評価表付き】
曹操を支えたのは、一癖も二癖もある「天才軍師」たちでした。 あなたの推しが見つかるかもしれない、最強の頭脳集団ランキングはこちらからどうぞ!
▶️🔗【曹操軍】軍師ランキングTOP10!なぜ魏は強かったのか?

仲達よ…ほんまに病弱やったんか? その“体力温存”の発想、ワシも採用したいのう!
諸葛亮との知略合戦!司馬懿はなぜ勝てたのか?


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
司馬懿は決して焦らず、諸葛亮を消耗させたのじゃ。
魏での活躍がわかったところで、次にどうしても気になるのは――やっぱり諸葛亮との知略合戦です。
「結局、司馬懿ってどうやってあの天才・諸葛亮に勝ったの?」
初心者なら一度は考えるこの疑問、実は三国志をグンと面白くする最大の見どころなんですよ。
だって、この二人はまるで水と油。諸葛亮は「攻めて攻めて攻めまくる」ド派手なチェス型、司馬懿は「じっと待って最後に勝つ」将棋型。動きの派手さでは孔明に軍配が上がりますが――最後に笑ったのは動かざる仲達。
この正反対のスタイルがぶつかり合って生まれるのは、ただの戦争じゃなくて知恵比べ。しかも、勝敗の鍵は意外にも「どっちが長くガマンできるか?」だったのです。
北伐は何回?どう防いだ?|攻める孔明 vs 守る仲達の「ガマン大会」
さて、まずは基本の疑問から!「諸葛亮の北伐って結局何回あったの?」と疑問に思う方も多いはず。答えは――合計5回!(多いわ!)。
諸葛亮は、魏を倒して漢という国を復活させるために、何度も何度も北上して攻めかかってきました。しかし、正面決戦で一気にカタをつけたい孔明に対して、司馬懿は正反対の作戦を取ります。
👉 正面からは絶対に戦わない!ひたすら守備を固めて、相手が自滅するのを待つ!
これって例えるなら――あなたが熱く語る上司に対して、「はい、はい、なるほど〜」と動かざる相づちを打ち続け、結局上司の方が疲れて声がガラガラになるのを待つようなもの!(笑)。地味ですけど、効果はバツグンなんです!
つまり、司馬懿の勝利は「ガマン大会の勝利」。戦って勝つのではなく、「相手に戦う気を失わせて勝つ」という、究極の省エネ戦法だったわけです。
五丈原で司馬懿は何をした?|「動かぬ勝利」の極致
次に有名なのが、「五丈原(ごじょうげん)の戦い」。これが、二人の最後の戦いになりました。
ここでも司馬懿は、徹底して守備を固めます。どんなに諸葛亮から「出てこいや!」と挑発されても、お茶をすすりながら「まあまあ、ご苦労様」と完全無視!
その結果、どうなったか?――にらみ合いが長く続きすぎたせいで、なんと諸葛亮の方が病気で倒れてしまうんです!😱
つまり――司馬懿は戦場で槍を交えて勝ったのではない!「誰よりも長く待てた」という我慢強さ(忍耐力)で勝ったんです。これが「動かざる参謀」の真骨頂!
関連記事👇
三国志の後半は話が難しくなりがち…。そんな人でも大丈夫! 複雑な5回の北伐を、豊富な図解とやさしい言葉でスッキリ整理しました。これで「後半はよく分からない…」を卒業して、最後までバッチリ楽しめます!
▶️ 🔗諸葛亮の5回北伐とその理由を徹底解説【三国志ファン必見
「死せる孔明、生ける仲達を走らす」とは?
さて、最後におなじみの名言!
「死せる孔明(こうめい)、生ける仲達(ちゅうたつ)を走らす」とは何か?
意味はシンプル。 👉 諸葛亮が死んだ後も、彼の威光(いこう)を恐れた司馬懿が、ビビって慌てて退却したという故事です。
どんだけカリスマやねん!とツッコミたくなりますが、これこそが、諸葛亮の天才ぶりと、司馬懿の用心深さを同時に表す名シーン!司馬懿は「絶対にだまされないぞ!」と、死んだふりまで疑ったんですよ。
ここまでで、「なぜ諸葛亮を退けられたのか?」が見えてきましたね。司馬懿は戦って勝ったというより、徹底して待ち続けて、相手を消耗させた男でした。
では、次は彼が魏の歴史をひっくり返した大事件――「高平陵の変」を見ていきましょう。ここで、「動かざる男」がついに人生最大の勝負に動きます!さあ、歴史が動く瞬間を覗き見しましょう!
🔗 あわせて読みたい!👇
「えっ、死んだ孔明に司馬懿が逃げた!?」という有名すぎる名言【死せる孔明、生ける仲達を走らす】。木像エピソードの真相や、史実との違いなどをちびキャラと一緒に爆笑解説しています。
▶️🔗死せる孔明、生ける仲達を走らすとは?|三国志の名言解説!
悩める君主の右腕にして、知略のバケモノたち!本気で強い軍師をまとめてみたよ🔥
▶️🔗三国志最強軍師5選!総合スコアS級

こら!死んでも怖がられるってどういうことやねん!
「高平陵の変」|“動かない男”がドーンと動いた日!


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
高平陵の変は、司馬懿が魏の実権を完全に奪った事件じゃ。
さあ、いよいよ司馬懿(しばい)さんが本気(ガチ)を出す時がやってきました!
これまで「動かない男」として、ひたすら守って、ひたすら待って勝利をかっさらってきた司馬懿さんですが、249年――ついにドッカーンと動きます。その大事件こそが高平陵(こうへいりょう)の変!
名前だけ聞くと「漢検の難しい漢字みたい…」と難しそうですが、かんたんに言えば「政敵をまとめて追い落として、魏(ぎ)の実権をガッチリ握ったクーデター」なんです!ここから魏は事実上、司馬家の天下へ!さあ、その中身をサクッとわかりやすく見ていきましょう。
高平陵の変とは?何が起きた?誰がどうなった?
高平陵の変、それは司馬懿の「のらりくらり」集大成!
当時、魏の国では、幼い皇帝の代わりに曹爽(そうそう)という偉い人が権力を独り占めしていました。司馬懿さんは、曹爽に「もうワシは病気でヨボヨボでーす👴」と完璧な役者ぶりで引退したフリをして、ただただ待っていたんです。
そして249年、旧正月。チャンス到来!皇帝と曹爽が、都を離れてお墓参り(高平陵)に出かけた一瞬のスキをついて、司馬懿は突如クーデターを決行!
つまり、「表向きは『曹爽が皇帝をないがしろにしているから、ワシが正しい道に戻す!』」と大義名分を掲げながら、実際は司馬懿さんが魏を乗っ取るきっかけを作った事件でした。これで魏は事実上、司馬一族の国にガラッと変わったんです。いやー、動くときは大胆すぎ!この大胆さを見習っていきたいですね。
高平陵の変の後、何が変わった?(三国志エンディングへGO!)
この事件を境に、魏の実権は完全に司馬家のものへ!
- 司馬懿が手に入れた政権は、まず息子の司馬師(しばし)へバトンタッチ!
- 司馬師は、さらに弟の司馬昭(しばしょう)へバトンを渡します!
- 司馬昭の息子こそが、超重要人物の司馬炎(しばえん)!
そして、この孫の司馬炎が、魏を滅ぼして**「晋(しん)」**という国を建国!バラバラだった中国を統一しちゃうんです!
こうして、三国時代は終わりを告げました!
つまり、高平陵の変は、「三国志のエンディングボタンを押した事件」だったわけです!
あの諸葛亮すら手を焼いた「動かない男」が、最後に歴史をひっくり返すなんて、人生って本当に最後まで何が起きるかわかりませんね!
ここまでで「高平陵の変=司馬懿が魏を完全に掌握したクーデター」だと、しっかり理解できましたね。忍耐の人・司馬懿が最後に見せたこの一手こそ、“勝つまで動かん”戦略の大フィナーレでした。
でも、物語はここで終わりません。司馬懿の死後、その後継ぎたち――息子の司馬師・司馬昭、そして孫の司馬炎がどう動いたのか?次で詳しく解説していきます!
関連記事👇
「えっ、この人が裏切り者!?」三国志の裏切りエピソード、予想以上にドラマチックです!▶️🔗【三国志の裏切り者ランキング】意外な理由と人物を徹底解説

おいおい、守り一辺倒やと思ったら、クーデターでドカーンて!動くときは派手すぎやろ!ワシもビビったわ!
司馬懿一族で天下を取ったドリームリレー!


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
司馬懿一族のリレーで三国志は終幕へ向かったのじゃ。
司馬懿(しばい)さんが「高平陵の変」というクーデターで魏(ぎ)の実権をガッチリつかんだあと、物語は次の世代、つまり息子たちへと引き継がれます。
「え、司馬懿が死んだらどうなったの?」
「誰が次に天下を動かしたの?」
そんな疑問はここで解決!じつは、この後の歴史は、まるで駅伝みたいに親子三代のバトンリレーで、三国志という長編ドラマがエンディングを迎えるんです!
まるで歴史版『大河ドラマ』のクライマックス!さっそく、司馬家の息子たちと孫の活躍を見て、歴史のゴールを一緒に見届けましょう!
司馬師と司馬昭のちがいは?―堅実兄vs野心家弟の好対照!
まずは司馬懿の二人の息子たち。この兄弟が、またキャラが濃くて面白いんです!
- 司馬師(しばし):長男
- 政治の手腕が抜群!お父さん譲りの冷静沈着さで、堅実に魏を運営し、司馬家の基盤を固めた人物です。例えるなら、ミスをしない安定感ある“官僚タイプ”。
- 司馬昭(しばしょう):次男
- あの有名な言葉「司馬昭の心、子どもでも知る」で知られるように、野心がダダ漏れ!
大胆な行動で魏の国を牛耳った、まさに“野心家タイプ”!「天下を取りたいんです!」って顔に書いてあったレベル(笑)。
- あの有名な言葉「司馬昭の心、子どもでも知る」で知られるように、野心がダダ漏れ!
つまり、兄は堅実な守り、弟は大胆な攻め――まるでドラマの主人公とライバルみたいな好対照ぶり!この兄弟の連携(?)が、司馬家の勢いをさらに強めたんですね!
司馬炎は何を成し遂げた?―三国志のエンディングを担当!
そして、バトンリレーのアンカーとして最後に登場するのが、司馬懿の孫・司馬炎(しばえん)!
この人が、とどめの一撃を食らわせました。彼は、魏という国を正式に滅ぼして、自ら皇帝となり「晋(しん)」を建国!そして、なんとバラバラだった三国(魏・呉・蜀)をついに統一してしまったんです!
言い換えれば、「じいちゃん(司馬懿)が何十年もかけてまいたタネを、孫の司馬炎がおいしく刈り取った」という構図。ここで三国志は完全に幕を閉じました!これぞ究極の家族経営!なんだか壮大すぎて、思わず元気が出てきませんか?
こうして、司馬懿→司馬師→司馬昭→司馬炎と、親子三代のバトンリレーで歴史は大きく動きました。つまり、三国志のクライマックスを飾ったのは“司馬一族の物語”でもあったのです。
では次に気になるのは――「そんな司馬懿って、どんな性格だったの?」というところですよね。実は、史実(正史)と小説(演義)では描かれ方がかなり違うんです。次は、司馬懿の性格と評価をわかりやすく解説していきましょう!

オレら親子3代で天下取ったで!ドヤァ!
ちなみに、今回の司馬懿たちに興味を持った方は、彼らの活躍をもっと深く知るためにおすすめの書籍もチェックしてみてください!
私が思わず笑ったり、泣いたり、吹き出したのがこちら👇
▶️ 🔗 三国志おすすめ本ベスト【7選】初心者から沼落ちまで
中でもおすすめは、『眠れなくなるほど面白い三国志』!👇
▶️ 🔗 三国志 わかりやすい本ならコレ!眠れぬ夜が続く「意外な1冊」とは?
読みながら、「司馬懿ってこんなに人間くさかったの!?」
「孔明って本当に死んでからも動くの!?」
とツッコミたくなる場面が満載でした(笑)
初心者でもスイスイ読めるのに、気づけば深みにハマってしまう一冊です。
「三国志って難しそう…」と思ってる人ほど、この1冊でイメージが変わりますよ!

馬に乗ってても読んじゃったわ!そしたら、木にドーンよ!!(ドーン)
👇【簡単リンク】『眠れなくなるほど面白い三国志』
(楽天/Yahoo/Amazonから選べます)
司馬懿の性格・評価(正史と演義の違い)「病弱フリ」は特技です!


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
司馬懿は忍耐強く、冷徹で、史実と演義で描かれ方が違うのじゃ。
さて、ここまでで司馬懿の“歴史的な勝利”はわかりました。でも、「この人、どんな性格やったん?友達になれる?」という疑問もありますよね。
そこでポイントになるのが、史実(正史)と小説(演義)での描かれ方のちがいです。
忍耐と用心深さ ― 病弱装い&女装でピンチ回避!
司馬懿は、とにかく「生き残る」ことを最優先にした人!
- 若い頃:病弱を装って、「ワタクシ、仕官なんて無理でして〜」と、曹操(そうそう)からのスカウトを何年も拒否!
- 危機を逃れる:敵からの挑発に女物の服を着て応じたり(!)、政敵の前ではボケたフリをしたり…。
つまり、彼は今日風にいえば「リスクヘッジ力おばけ」!ここまで徹底して自分を守ると、もはや特技の域ですね!
彼の用心深さを知ると、「焦らず待つ」ことの大切さが身に染みて、急に大人な気分になってきます!
正史 vs 演義 ― どこがちがう?「噛ませ犬」説の真相!
| 視点 | 史実(正史)での評価 | 小説(演義)での描かれ方 |
| 性格 | 冷静沈着な戦略的実務家。 | 小心者で卑怯なキャラとして描かれることが多い。 |
| 役割 | 知略と忍耐で魏を支えたキーパーソン。 | 諸葛亮(孔明)を引き立てるための“噛ませ犬”役。 |
しかし、両方に共通しているのは「勝つまで動かない忍耐型」だという点。描かれ方が違っても、司馬懿の本質はブレていないのです。どちらの司馬懿が好きか、考えてみるのも楽しいですね!

オレの真逆やな!考える前に突っ込んでまうわ!
関連記事👇
「司馬懿は忍耐型の軍師でしたが、じゃああなたは?」
性格診断感覚で楽しめるのがこちら👇
▶️🔗 【軍師診断】あなたはもしも軍師だったら誰タイプ?
意外と“司馬懿タイプ”が出たらビックリですよ(笑)
三国志の戦場や軍議の裏には、必ず“酒”がありました。
実はあの伝説の名馬「赤兎馬」、現代では“飲める赤兎馬”として蘇っているんです。
▶️🔗 赤兎馬とは?史実&焼酎の秘密はこちら
「関羽を支えた赤兎馬」と「あなたの晩酌を支える赤兎馬」
歴史と現在をつなぐ“ロマンの架け橋”が、この焼酎です。

ちょっと待て、張飛!赤兎馬は一気飲みするもんじゃないぞ!
👇【簡単リンク】本格芋焼酎「赤兎馬」
(楽天/Yahoo/Amazonから選べます)
今夜は“三国志の宴”に参加しませんか?
司馬懿まとめ|初心者が持ち帰る“一言”とは?

🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
司馬懿は“勝つまで動かない”究極の忍耐型戦略家じゃ。
司馬懿とは?――三国志初心者のあなたへの答えは、もうシンプルです!
彼は「動かないことで、勝ちと天下をつかんだ人」です。
あの諸葛亮に正面で勝ったわけではなく、徹底した消耗戦と忍耐で退けました。さらに最後はクーデターで魏を掌握し、孫の代で三国時代を終わらせたのです!
現代にたとえるなら、「焦らずチャンスを最高のタイミングで待つ戦略家タイプ」!忍耐とタイミングの大切さを教えてくれる最強の存在です。これで、もう司馬懿のことはバッチリ!三国志がグッと楽しくなったはずですよ!
さあ、あなたも「動かざる参謀」から謎の元気をもらって、今日を乗り切っちゃいましょう!

わしも忍耐型じゃが、待ちすぎて腰痛めたわい!司馬懿の真似はほどほどにの!
⚔️「司馬懿とは?初心者向けにわかりやすく解説」
諸葛亮を退けた“動かない知略”の正体をやさしく解説!
スマホからでもサクッと読める保存版です。気に入ったらXでシェアしよう。
📥【画像を長押し or タップで保存】
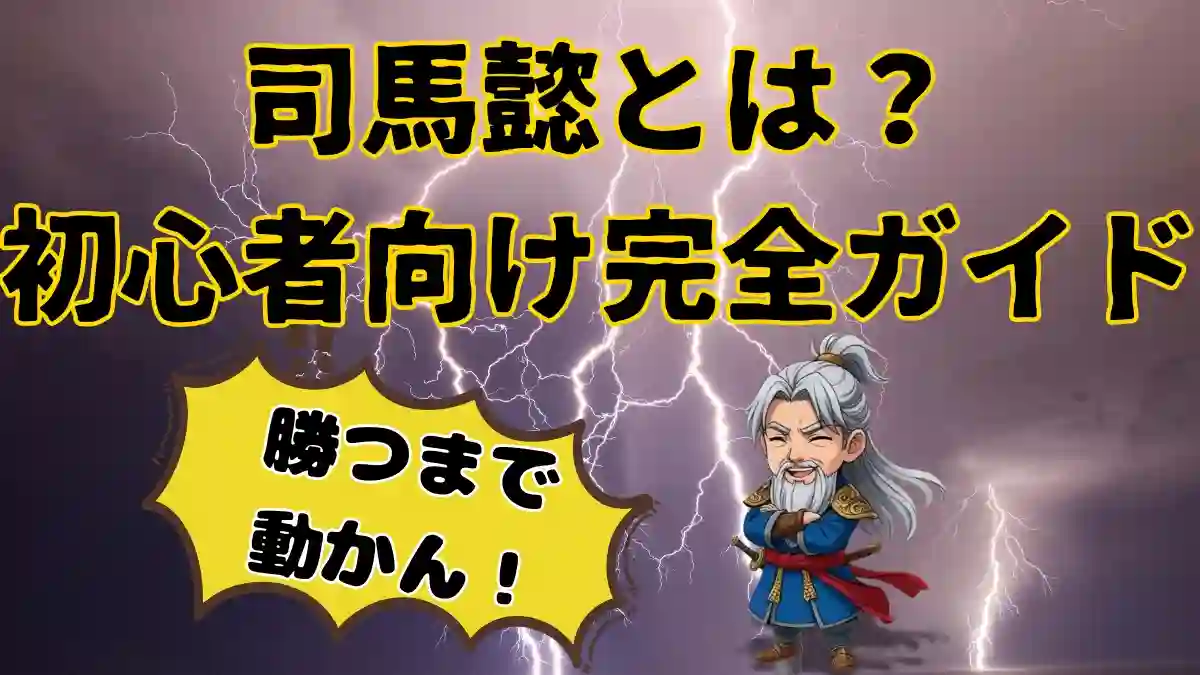
👇そのあと、下のボタンからXでシェア!
 「シェアしてから戦にでる!それが張飛流よぉぉぉーッ!!」
「シェアしてから戦にでる!それが張飛流よぉぉぉーッ!!」
📚 あわせて読みたい
もしあなたが、「もっと三国志の世界に浸りたい!」「あの英雄たちのことをもっと詳しく知りたい!」と思ったなら、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください!きっと、さらに深く三国志を楽しめるはずです!( ・`ω・´)
👀おまけ:もっと三国志を楽しみたい人はこちら!
三国志好きにはたまらないif企画や深掘り記事が盛りだくさん!
私もブログを始めたころからずっと憧れている、「はじめての三国志」さんの記事はこちら👉
👉[対決]諸葛亮対司馬懿:策略の神々、誰が頂点に立つ?
気になったら、ぜひのぞいてみてね!🙏✨
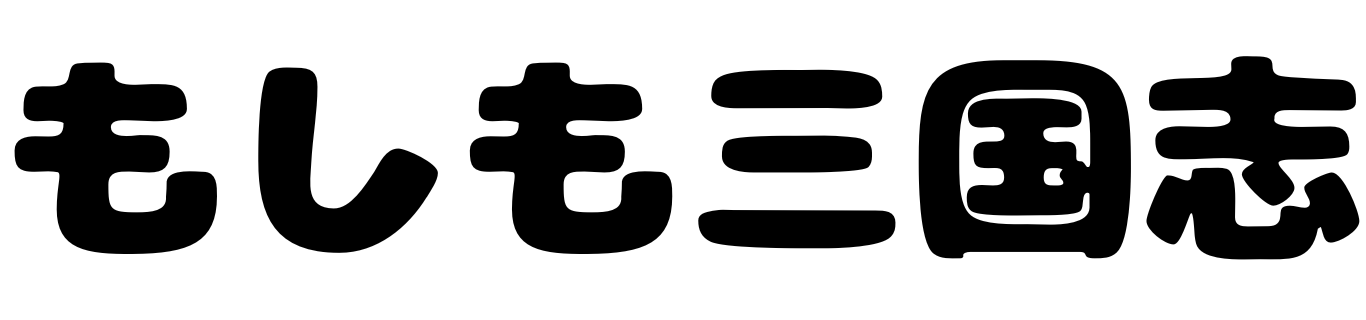
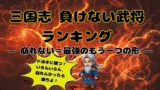

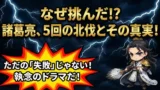



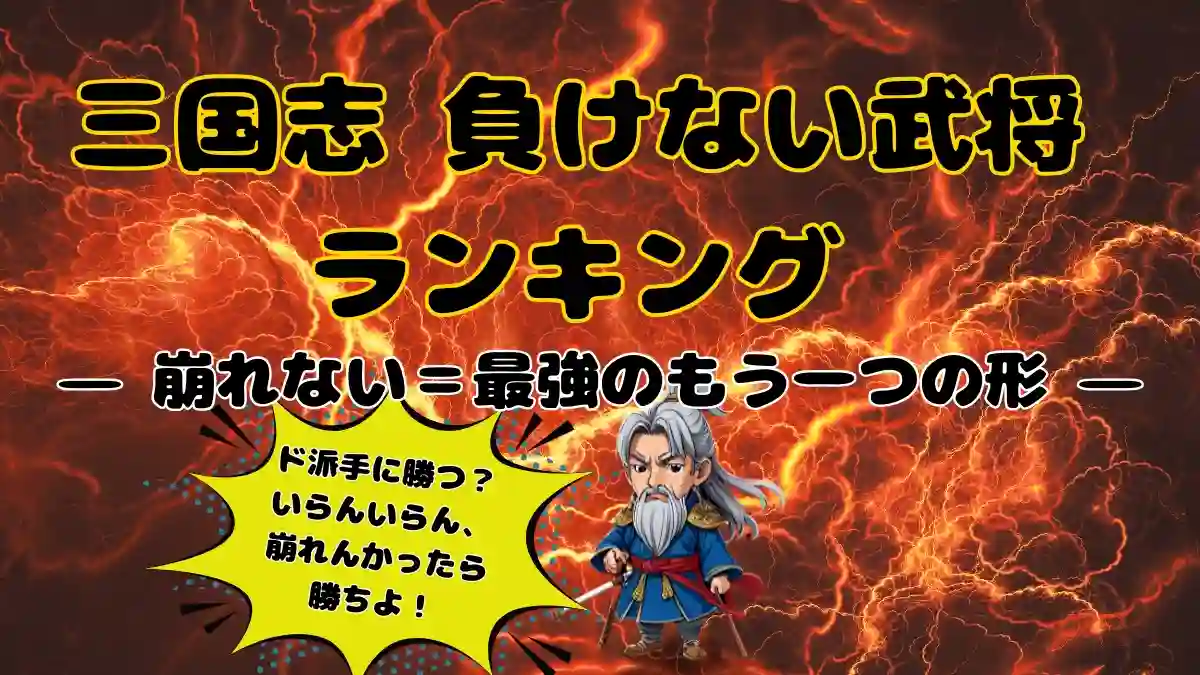

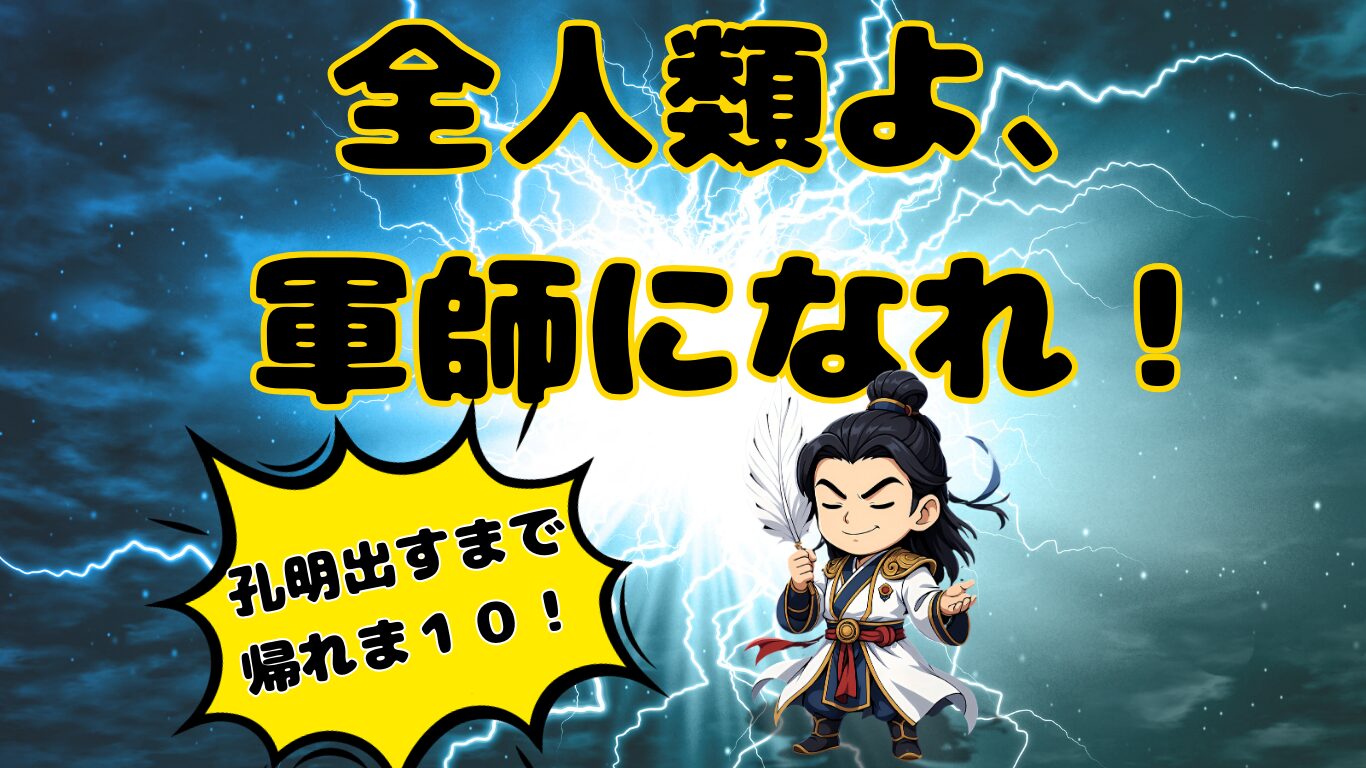





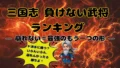

コメント