周瑜 赤壁の戦いって聞くと、「なんだか難しそう…」「歴史の話って堅苦しいんじゃ?」と尻込みしてしまうあなた!
でも大丈夫、この記事は三国志ビギナーさん向けに、むずかしい話をぜんぶゆるっとわかりやすく、しかもクスッと笑える感じでお届けします。
実は周瑜、ただの軍師じゃなくて「イケメンで頭も切れる」超人気キャラ。
でも意外と知らない彼の生涯や赤壁での大活躍を、7つの真実に分けてまるっと解説。読み終わったころには、「三国志って面白い!」って思えるはず。だから、一緒に楽しく学んでみませんか?

利を見ては動くべし!お得な情報、見逃すなよ?
周瑜とは?三国志のイケメン軍師の基本プロフィールをチェック!


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
周瑜はイケメン軍師、美周郎の名に恥じぬ名将じゃ。
周瑜と聞けば、多くの人が「三国志のイケメン軍師!」と即答しますよね。
確かにその美貌は伝説級ですが、彼の真価は見た目だけではありません。
ずば抜けた戦略眼と人心掌握術で、数々の戦いを勝利に導いた切れ者なのです。
では、なぜ彼は「美周郎」と呼ばれたのでしょうか? そこには単なる容姿以上の意味が隠されています。
今回は、周瑜の基本プロフィールから「美周郎」の由来、さらに波乱に満ちた生い立ちと出世の道のりまでを、初心者でも笑いながらスラスラ読めるように解説します。
読み終わる頃には、あなたもきっと「周瑜推し」になっているはずです。
周瑜とは?三国志を彩る「美周郎」イケメン軍師の魅力プロフィール
周瑜(しゅうゆ)は、中国三国時代の呉を代表する武将であり軍師です。
歴史書『三国志』では、その端正な顔立ちと立ち居振る舞いから「美周郎(びしゅうろう)」の異名で知られています。
残念ながら身長や顔立ちの細かな記録は残っていませんが、当時の記述には「容姿端麗で、人々を惹きつけるオーラがあった」とあります。
しかも、ただの見た目だけイケメンではありません。周瑜は戦術家としての能力も抜群で、冷静な判断力と大胆な行動力を併せ持っていました。そのため孫策や孫権といった呉のトップからも絶大な信頼を受け、重要な戦いを任されることに。
つまり、周瑜の魅力は「美貌+才知+人望」という三拍子そろったパーフェクト軍師ぶりにあります。三国志ファンはもちろん、これから三国志を学ぶ人にとっても、まず押さえておきたい人物なんです。
「美周郎」とは?三国志の周瑜に贈られたカッコよすぎる称号の意味
「美周郎(びしゅうろう)」?「ただのイケメンあだ名でしょ?」
と思ったあなた、実はもっと深い意味があるんです。
まず「美」は見た目の美しさだけでなく、「優れている」「すばらしい」という称賛のニュアンスを含まれているんです。
そして「周郎」の「郎」は若者や若い男性を指す言葉。つまり、「美周郎」は「容姿も才能も抜群な若き周瑜」という、最大級の敬意をこめた呼び名だったのです。
周瑜は若くして軍事・政治の両面で頭角を現し、その華やかな存在感は呉のエース級。
現代に例えるなら「容姿端麗・頭脳明晰・人望ありの30代で上場企業社長」くらいのパーフェクト感です(笑)。
このあだ名が後世まで語り継がれるのも納得ですよね。
周瑜の生い立ちと出世の道|赤壁を制した若き才覚の舞台裏
周瑜(しゅうゆ)は揚州・廬江(現在の安徽省)出身。
まず言っておくと、彼は単なる「見た目イケメン」ではありません。若い頃から学問と武術を両立し、しかも人間関係を巧みに築くタイプだったのです。
だからこそ、早くから周囲の信頼を集め、孫策→孫権という呉のリーダー層に抜てきされました。
さらに、赤壁の戦いでは周瑜の指揮力が光ります。つまり、冷静な戦略眼と迅速な決断が合わさって、あの大勝につながったわけです。
ところで、華やかな成功の裏には嫉妬もつきもの。実際に諸葛亮との微妙な力関係は、後世の物語でも大きな見せ場になります。
とはいえ、結局のところ周瑜の出世は「見た目+コネ」ではなく「実力+人望」がベース。
ですから、彼を理解するには生い立ちと初期の人脈、そして赤壁での振る舞いをセットで見ることが鍵(カギ)なんです。
最後に一言。周瑜のどの“伝説エピソード”が一番気になりますか?
コメントで教えてくださいね!

おい!イケメンばっかり褒めやがって、俺の出番はねぇのかー!?(笑)
周瑜の官職と役割|中護軍・江夏太守から見る赤壁の立役者の仕事


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
ふむ…周瑜は戦略家であり政治家じゃ。二つの要職を兼ね、呉を支えた男よ。
「周瑜って、赤壁の戦いで活躍した人だよね?」──はい、それも正解。
でも、それだけで終わらせるのはもったいない話です。
実は周瑜は、中護軍(ちゅうごぐん)と江夏太守(こうかたいしゅ)という、呉の軍事と政治を同時に握るスーパー要職を務めていました。
名前だけ聞くと「何そのカタい肩書き…」って感じですが、当時の呉では超エリートポジション。つまり、赤壁の英雄であると同時に、国家運営のキーパーソンでもあったわけです。
では、一体どんな仕事をしていたのか?
そしてなぜ彼は呉にとって欠かせない存在だったのか?
その答えを、初心者でもスラスラ理解できるように、そして時々クスッと笑えるようにご案内します。
これを読めば、あなたの周瑜のイメージが“戦の達人”から“戦+政治の二刀流ヒーロー”へとレベルアップすること間違いなし!
中護軍・江夏太守とは?歴史的意味と役割をわかりやすく解説
まず、「中護軍(ちゅうごぐん)」とは何をする役職なのか。
一言でいえば、呉の中央防衛と将軍たちのまとめ役です。
孫権直属の軍を守ると同時に、各地の将軍同士が衝突しないよう間を取り持つ──まさに軍の空気清浄機みたいな存在。
これがいないと、戦う前に内輪揉めで国が傾きかねません。
一方、「江夏太守(こうかたいしゅ)」は、今の湖北省あたりを治める地方長官のこと。
この江夏という土地、場所がまた厄介でして…荊州と国境を接しており、曹操や劉備とバチバチやり合う火薬庫のような地域だったんです。
つまり周瑜は、「本社の防衛責任者」兼「国境の知事」という二刀流ポジションを同時に担当していたわけです。
これ、現代でたとえるなら──大企業の総務部長をしながら、海外支社の支社長もやってるようなもの。
しかもその海外支社、すぐ隣がライバル企業の本社ビルみたいな立地です。責任の重さ、もう想像つきますよね?
周瑜の政治的・軍事的立場と呉への影響力
中護軍としての周瑜は、ただ命令を出すだけの将ではありませんでした。
まず兵たちの士気をググッと引き上げ、次に「これからどう戦うか」という大きな戦略の舵を切る──いわば軍のカリスマ監督兼GMのような存在です。
そして江夏太守としては、国境線の防衛を固めながら、隣国との微妙な関係をうまく調整する外交官でもありました。
しかも相手は曹操や劉備。気を抜いた瞬間に戦争が起きかねない、超デリケートなポジションです。
この二つの役割は、赤壁の戦いで最大限に活かされます。孫権が「曹操と戦う!」と決断できたのも、周瑜の戦略眼と現場での采配が後ろ盾になっていたからこそ。
もし彼がいなければ、呉は迷いの中で滅びていたかもしれません。
しかも彼の影響力は軍事だけにとどまりません。若くして孫権の厚い信頼を勝ち取り、政策や人事にも意見できる立場となり、長期的に呉の安定を支え続けました。まさに「呉の屋台骨」─戦でも政治でも、国を丸ごと支える存在だったのです。

周瑜殿、ちょっとは休んでください…!こっちも体力が持ちません!
赤壁の戦いにおける周瑜の神采配と勝利の真相


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
赤壁の勝利は偶然ではない。周瑜の頭脳と度胸の勝利じゃ。
「赤壁の戦い=諸葛亮の奇策」というイメージ、あなたも持っていませんか?
実はそれ、半分正解で半分間違い。真の司令塔は、呉の若き天才軍師・周瑜でした。
彼は綿密な戦略を立て、10万を超える曹操の大軍を相手に、わずかな兵力で歴史的大勝利を収めます。
しかもこの戦い、ただの海戦ではありません。三国の勢力図を塗り替え、中国史に「赤壁前」「赤壁後」という時代区分を作ったほどの大事件だったのです。
本記事では、赤壁の戦いの全体像から、周瑜の緻密な作戦、諸葛亮との意外な関係、さらに魯粛を呉に引き入れた人脈戦略まで、初心者でもスラスラ読めるように、笑いも交えて徹底解説します。読後にはきっと「周瑜こそ真のMVPだった!」と納得してしまうはずです。
赤壁の戦いの全体像をざっくり解説|三国時代の勢力バランス
西暦208年──天下統一を目前にした曹操が南へ進軍し、まず荊州を制圧。勢いそのままに、次の獲物として狙いを定めたのが孫権率いる呉でした。
その頃、荊州から命からがら逃れた劉備は、このままでは曹操に飲み込まれると判断し、孫権と手を結びます。こうして「北の曹操」「南の孫権」「その間に劉備」という三すくみ状態が誕生。
ここに同盟や駆け引きが絡み、緊張は最高潮に。
この構図こそが「赤壁の戦い」の舞台です。ただの一地方の戦いに見えて、実は三国時代のパワーバランス全体を揺るがすビッグイベント。まさに、中国史が大きく方向転換した瞬間だったのです。
関連記事👇
「三国志といえば赤壁!」…ってほんとにあったの?そのド迫力バトルの裏側、気になりませんか?▶️🔗赤壁の戦いは本当にあった?歴史の真実と三国志の謎を徹底解説
赤壁の戦いが初めてでも大丈夫。図とストーリーで「誰が・どこで・どうしたか」がスッと入ります。▶️🔗赤壁の戦い決定版|簡単にわかる勝因・敗因と魏・呉・蜀の行方
周瑜の戦略と采配|なぜ彼が勝利の立役者なのか
曹操軍の兵力はなんと約20万──と言われていますが、史料によっては
「実はもっと少なかった説」もあり。
とはいえ、対する呉・蜀連合軍はせいぜい数万。数字だけ見れば、呉は圧倒的不利でした。
そこで登場するのが、若き司令官・周瑜の冷静な戦略眼。「川を制する者は戦を制す」と読んだ彼は、広大な長江を舞台に戦うことを決断します。
陸で戦えば騎馬の多い曹操軍が有利。しかし、水上戦なら慣れない敵を翻弄できる。周瑜は地形と呉の得意分野を最大限活かし、戦場を“水上限定”にしてしまったのです。
結果、曹操軍の機動力を完全に封じ込み、勝利への布石を打つことに成功。この判断こそが、
「赤壁の戦い」における勝利の第一歩でした。
火計の実行と諸葛亮との連携
「火計」と聞くと、つい諸葛亮を思い浮かべがちですが──実際に作戦の指揮を執り、準備の細部まで整えたのは周瑜でした。
彼は、風向きの変化、船団の配置、火矢を放つタイミングまで緻密に計算。
さらに、劉備陣営とも密に連携し、全員が同じ瞬間を狙えるよう段取りを整えました。
一方の諸葛亮は、気象予測という“神業”でサポート役に徹し、絶妙なタイミングで東南の風を予見。これにより、曹操軍の船はまるで炎の通り道に並べられた駒のようになり、一気に炎上。
こうして長江は一瞬にして火の海と化し、曹操軍は大混乱。周瑜と諸葛亮、ライバル同士でありながらも、戦場では息の合った連携で歴史的勝利をつかみ取ったのです。
諸葛亮との複雑な関係|嫉妬か、リスペクトか
『三国志演義』では、周瑜が諸葛亮の才能に嫉妬して「く…やられた!」と悔しがる場面がたびたび描かれます。
しかし、これはあくまでフィクション寄りの演出。史実の記録を見る限り、赤壁の戦いでは二人はむしろ協力関係にあり、作戦の成功のために役割を分担していました。
とはいえ──同年代で、しかもどちらも“軍略の天才”。ライバル意識がまったくなかった…というのも想像しづらいところ。戦後の二人の関係は、まるで「お前、なかなかやるな」「そっちこそな」という目線を交わすスポーツ選手同士のようだったかもしれません。
結局のところ、周瑜と諸葛亮は「嫉妬で動く敵」ではなく、「刺激し合うライバル」だった可能性が高いのです。そして、このライバル関係こそが、赤壁の奇跡を生んだ最大のスパイスだったのかもしれません。
👉「そもそも諸葛亮ってどんな人?」と思ったあなたにぴったりの記事があります♪
ちびキャラと一緒に、諸葛亮(しょかつりょう)のすごさや性格、名言まで楽しくわかる解説はこちら▶️🔗諸葛亮ってどんな人?初心者でも5分でわかる超かんたん解説!
「火計発動ーーッ!!」
東南の風を操り、連環の計で曹操を追い詰めた諸葛亮。赤壁の戦いを制した天才戦略を詳しく紹介!▶️🔗諸葛亮の火計とは?東南の風と連環の計で赤壁を制した天才戦略
魯粛を呉に引き入れた人脈戦略
周瑜のすごさは「戦う」だけじゃありません。人を見る目=人脈戦略でも一級品でした。まず、温厚で頭の回転が速い魯粛(ろしゅく・字は子敬)に早くから注目し、その見識と外交センスを高く評価。周瑜が橋渡し役となって孫権に推挙・引き合わせたことで、魯粛は呉の中枢へと加わります。
そして赤壁の戦い後、魯粛は孫権の右腕として劉備との同盟維持や対曹操の交渉をリード。さらに国境管理や荊州問題でも実務を仕切り、呉の対外戦略の司令塔に。
言い換えれば、周瑜は「戦場の名将」であると同時に、組織に必要な人材を見抜いて口説くヘッドハンターでもあったわけです。
だからこそ、周瑜の勝利は“火計”だけの結果ではありません。適材適所の人材配置という地味だけど超重要な仕事が、のちの呉を支える土台になったのです。
さて質問。あなたが呉の採用担当なら、最初にスカウトするのは即断即決の周瑜? それとも堅実交渉の魯粛? コメントで推しを教えてください!
関連記事👇
赤壁の戦いの舞台裏で“外交の舵取り”を担ったのが魯粛。彼の活躍や人物像をもっと知りたい方は ▶️🔗魯粛とは?【初心者向け】赤壁を動かした“外交の要”をやさしく解説

いや、僕を口説いたのは酒じゃなくて、周瑜さんの笑顔ですから!
周瑜の人柄と意外すぎる逸話集|武将の魅力を深掘り


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
戦場も宴も支配する、それが周瑜じゃ。
赤壁の天才司令官として知られる周瑜。ですが彼の魅力は、戦場だけじゃ語り尽くせません。
宴席で見せたユーモア、驚くべき音楽の才能、そして仲間への思いやり…まるで戦う王子様みたいな存在でした。そんな人柄に惚れ込んだ武将も多く、敵でさえ「アイツ、ちょっと好きかも」と思ったとか。
この記事では、歴史書では語られにくい周瑜の意外すぎる逸話と人気の秘密を、笑いを交えてたっぷりご紹介します。
宴席での逸話|音楽の才能と“絶対音感”伝説
周瑜といえば「赤壁の英雄」というイメージが強いですが、実は音楽界に転職しても食べていけそうなほどの耳の持ち主でした。
ある宴席では、琴の音がほんの一音ズレただけで即座に「ストップ!」。演奏者を呼び戻し、「そこ、半音下げようか」とピンポイントで指摘したそうです。まさに戦場では采配の天才、宴では音楽ディレクター。
しかも驚くべきは、その場の空気。普通なら演奏者も冷や汗モノですが、周瑜の軽妙な仕切りと笑顔のおかげで、場はむしろ大盛り上がり。「いや将軍、耳どうなってるんですか!?」とツッコミが飛ぶほどだったとか。
この逸話からわかるのは、周瑜の耳が天才レベルなだけじゃなく、人を緊張させずにのせる場のプロデュース力まで兼ね備えていたということ。だからこそ、戦場でも宴席でも人心をつかんで離さなかったのです。
性格分析|豪快さと繊細さを併せ持つ武将
周瑜の魅力をひと言でいうなら、「でっかく動いて、細かく気づく人」。
戦場では**「今だ、突撃!」**と豪快に号令を飛ばし、まるで一手先どころか三手先まで見えているかのような采配を振るいました。
ところがその一方で、戦略を練るときは地図の端っこの川幅まで計算し、敵将のクセや疲れ具合までチェックする慎重派。
宴では大笑いしながら酒をあおり、仲間を巻き込んで盛り上げるムードメーカー。それなのに、戦略会議になると相手のまばたきや表情の変化まで読み取っていたと言われます。**まるで「笑顔のスナイパー」**ですね。
この豪快さと繊細さの二刀流こそ、部下からも敵からも一目置かれた理由。カリスマ性は、ただのリーダーシップではなく、この絶妙なバランスから生まれていたのです。
人気の秘密|ビジュアル・実力・人間味の三拍子
周瑜の人気を語るなら、この三つは外せません——ビジュアル、実力、人間味。まず見た目、背が高くて端正な顔立ち。歴史書にも「美周郎」と記され、当時の女性たちの心をわしづかみにしていました。
次に実力。若くして中護軍、そして赤壁の戦いの総司令官に抜擢されるほどの軍才は、本物中の本物です。しかもそのリーダーシップは部下をビビらせるのではなく、自然とついていきたくなるタイプ。
そして人間味。戦場では厳しい判断を下しつつも、仲間を思いやり、宴では場を明るくするムードメーカー。現代でたとえるなら、戦場に現れる完璧すぎるアイドル兼カリスマCEO。そんな存在、モテないわけがありません。
だからこそ、周瑜は2000年たった今も「イケメン武将ランキング常連」の座を譲らないのです。

顔と才能と人気…俺にも少し分けろや!
関連記事👇
「顔面偏差値でも戦えます。」歴史に名を残したイケメン武将たちをランキング形式で大発表!あなたの推しは何位? ▶️🔗三国志イケメンランキングTOP5!初心者でも分かる魅力解説」
周瑜の晩年と評価|赤壁後の栄光と早すぎた死


🗨️ 要するにこういうことなんじゃよ
周瑜は赤壁後も攻めの手を緩めなんだが…志半ばで病に倒れたのじゃ。
赤壁の戦いで大勝利――「周瑜伝説、ここに完結!」と思ってる人、ちょっと待ったぁ! 本当の周瑜ドラマは、その後からが本番なんです。天下統一に向けて次の一手を打とうとしていた周瑜。
しかし…歴史は時にドS。彼は36歳という若さで、この世からログアウトしてしまいます。
この記事は、「赤壁の後、周瑜って何してたの?」とモヤモヤしてる三国志ファンや、「死因は本当に嫉妬だったの?」と気になって夜も眠れない歴史クラスタ向けにお届けします(※寝てください)。
読み進めれば、赤壁後の周瑜がどんな戦争プランを立てていたのか、どうして急逝したのか、そして正史と『三国演義』での評価の違いまでスッキリわかります。さらに、「嫉妬死説」を軽く一刀両断し、現代的に見た周瑜の再評価ポイントもご紹介。
要するに、この記事を読み終わる頃には――「え、周瑜ってイケメン司令官だけじゃなく、戦略も外交も人材スカウトもやってたマルチプレイヤーだったの!?」とドヤ顔で語れるようになります。もう飲み会で「三国志の話は長くなるからやめて」と言われても気にしないでOK。根拠は正史と歴史研究書がガッチリ保証してます。
赤壁の戦い後の周瑜の活躍と死因説|天下統一のシナリオもあった!?
赤壁で曹操を“火の海BBQ”にした周瑜。普通なら「いや〜やり切った!」って引退してもおかしくないのに、この人は違いました。
勝利の勢いそのままに、荊州へGO!残党はサクッと撃破、劉表の旧勢力もちゃっかり吸収。さらに、蜀との同盟も絶妙にキープして、孫権の領土をぐいぐい拡大。
まさに戦場の司令官+外交官+都市開発部長を兼任していたわけです。
しかも頭の中では、もっと壮大な計画が進行中。それが「天下統一ロードマップ」。
ステップ1:荊州を完全掌握。
ステップ2:益州(四川あたり)をゲット。
ステップ3:長江を制してドーンと中原進出!
…はい、完全に“リアル三国志無双モード”です。
ところが!西暦210年ごろ、遠征の途中で突然の病に倒れます。史書には「36歳で病没」としかなく、短命の理由はミステリー。
- 疾病説(過労+持病のコンボ)
- 急病説(感染症とか心臓疾患とか急展開系)
- 創作説(例の“諸葛亮に嫉妬して吐血”ネタ)
現代の研究では病死説が有力ですが、小説『三国演義』の影響で「嫉妬で死んだ武将」というインパクトキャラに…。
いやいや、現実の周瑜はもっと冷静で賢い人だったはず!もしあと10年生きていたら、三国志の地図はガチで塗り替えられていたかもしれません。
三国志での周瑜の評価と後世のイメージ|イケメン司令官、嫉妬キャラに改造されるの巻
史実の周瑜って、実は超優等生なんです。
正史『三国志』では「胆力(度胸)+度量(包容力)=最強」という、
まるで戦国武将界のオールラウンダー。
赤壁での大勝利はもちろん、その後も孫権の右腕として領土拡大にフル稼働。
宴会ではムードメーカー、戦場ではカリスマ司令官…欠点探しがむしろ難しいレベル。
ところが! 後世の小説『三国演義』で、諸葛亮を引き立てるためにまさかのキャラ改造。
「孔明…またお前か!(ゴホッ!)」みたいな、嫉妬で吐血するイケメンという謎属性を付与されます。
これが江戸時代の舞台やドラマでもウケちゃって、**「史実の周瑜=頼れる参謀」「演義の周瑜=嫉妬で寿命削る美形」**という二重人格みたいな扱いに。
でも現代では、SNSや歴史解説系YouTuberの影響で「いや、周瑜めっちゃできる人じゃん!」と再評価ラッシュ。
- 知略:赤壁だけじゃない、天下を見据えた戦略家
- 武勇:荊州攻略や遠征の陣頭指揮
- 人望:孫権からも部下からもモテモテ
この“三拍子”が揃ってる武将はかなりレア。X(旧Twitter)でも「もしあと10年生きてたら魏も蜀も終わってた説」がバズってます。赤壁の勝利しか知らない人は、ぜひこの“本当の周瑜”を知って、歴史の推しを更新してください。

周瑜があと10年生きてたら…オレ、天下獲ってたぞ!
ちなみに、今回のイケメン武将周瑜に興味を持った方は、彼らの活躍をもっと深く知るためにおすすめの書籍もチェックしてみてください!
私が思わず笑ったり、泣いたり、吹き出したのがこちら👇
▶️ 🔗 三国志おすすめ本ベスト【7選】初心者から沼落ちまで
「三国志どれ読む?」の答えがこれ。
吉川英治版はキャラも戦も濃厚で、読破後の達成感が別格。
まずはこの一冊で、三国志の沼へ。

迷ってる時間が一番もったいねぇ!今こそ、あの戦場へ行くぞォ!

人生の戦術書は『三国志』(吉川英治)(Amazon)で決まりや。 読まへんのは、「三顧の礼を門前払い」するくらい損してるで!

毎日の通勤時間、スマホを眺めるだけで終わらせていませんか?
Amazonオーディブルの「聴く三国志」なら、3ヶ月99円の期間中に全巻制覇も可能です。 時間をドブに捨てたくない方は、今すぐ試してみてください。
周瑜をもっと深く知るための関連記事紹介|次回予告はこうだ!
さて、ここまでで周瑜の魅力にすっかりハマった皆さん。
でも本当に面白いのはこれからなんです。赤壁シリーズ、まだまだ続きます!
今後の公開予定はこちら!
- 「諸葛亮の火計の真相」
→ あの夜、誰が火をつけたのか?歴史ファンの口論を500年分まとめました。
▶️🔗諸葛亮の火計とは?東南の風と連環の計で赤壁を制した天才戦略 - 「曹操の南征と赤壁敗北の背景」
→ 天下の曹操がなぜ南でズタボロ?その裏で動いていた“勝負を決めた理由”とは。
▶️🔗曹操と赤壁の戦い|なぜ負けた?南征の目的と兵力・敗因を解説 - 「赤壁直前の勢力図」
→ 孫権・劉備・曹操の位置関係が一目でわかる地図つき!戦う前から勝敗のヒントが隠れていました。
▶️🔗赤壁の戦い 勢力図|三国志の地図でわかる魏・呉・蜀と呉蜀同盟【208年・図解】
そして最後は…
- 「赤壁の戦い完全解説(決定版)」
→ これこそシリーズの集大成。読めばあなたも“赤壁博士”に昇格!飲み会での歴史マウントはほぼ無双状態。
▶️🔗 赤壁の戦い決定版|簡単にわかる勝因・敗因と魏・呉・蜀の行方
つまり、この順番で読めば、最終記事で「全部わかった感」を味わえる設計。最後は渾身の勝負記事で、あなたを赤壁の戦場に放り込みます。

最後まで読まぬ者は、戦の流れを語る資格なしじゃ!
💥全人類よ、周瑜の真実に震えろ!
赤壁の天才司令官・周瑜、その生涯と知られざる7つの真実をSNSで広めよう!
📥【画像を長押し or タップで保存】

👇そのあと、下のボタンからXでシェア!
 「シェアしてから戦にでる!それが張飛流よぉぉぉーッ!!」
「シェアしてから戦にでる!それが張飛流よぉぉぉーッ!!」
もしあなたが、「もっと三国志の世界に浸りたい!」「あの英雄たちのことをもっと詳しく知りたい!」と思ったなら、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください!きっと、さらに深く三国志を楽しめるはずです!( ・`ω・´)
👀おまけ:もっと三国志を楽しみたい人はこちら!
三国志好きにはたまらないif企画や深掘り記事が盛りだくさん!
私もブログを始めたころからずっと憧れている、「はじめての三国志」さんの記事はこちら
👉🔗周瑜は家柄で孫策を上回るのになんで独立しなかった?[孫策の配下]ではなかったってホント! 気になったら、ぜひのぞいてみてね!🙏✨
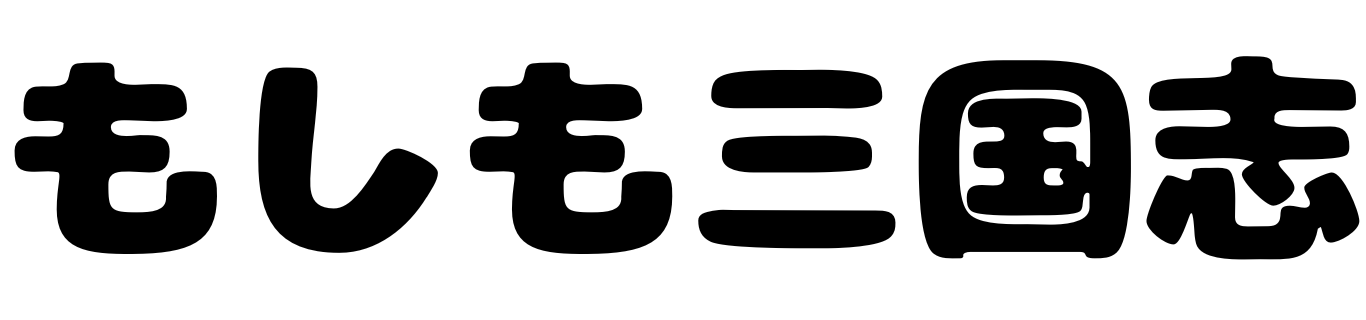

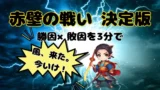

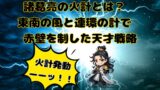
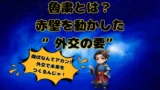


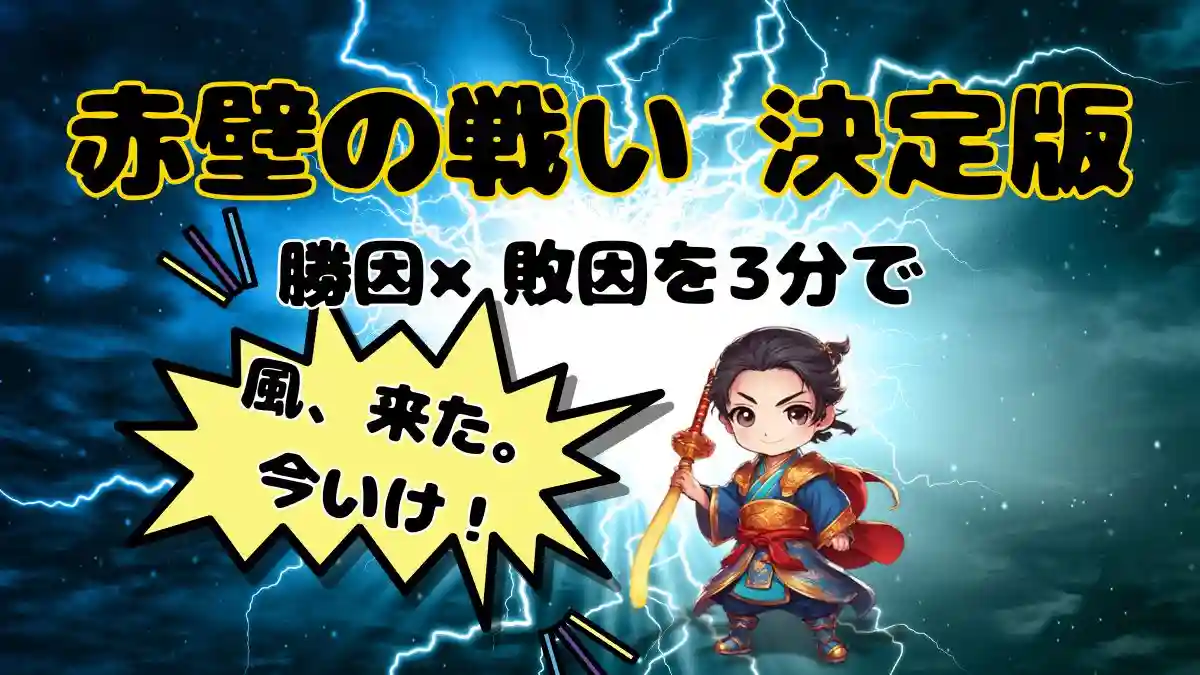
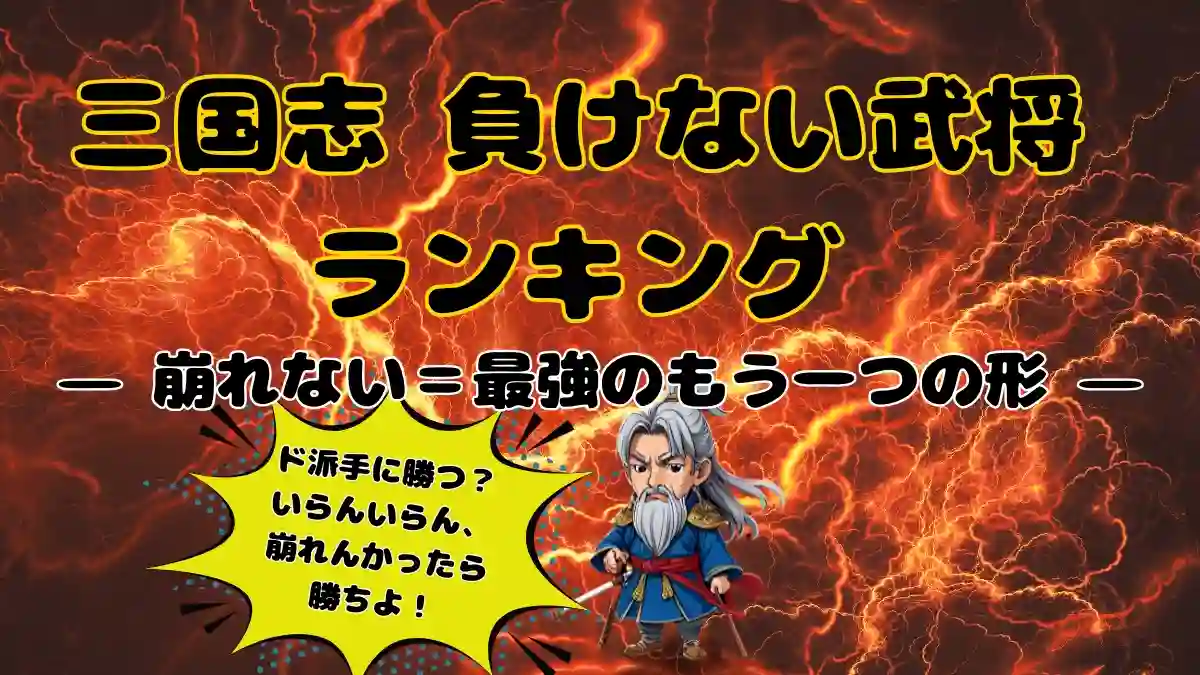





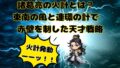
コメント